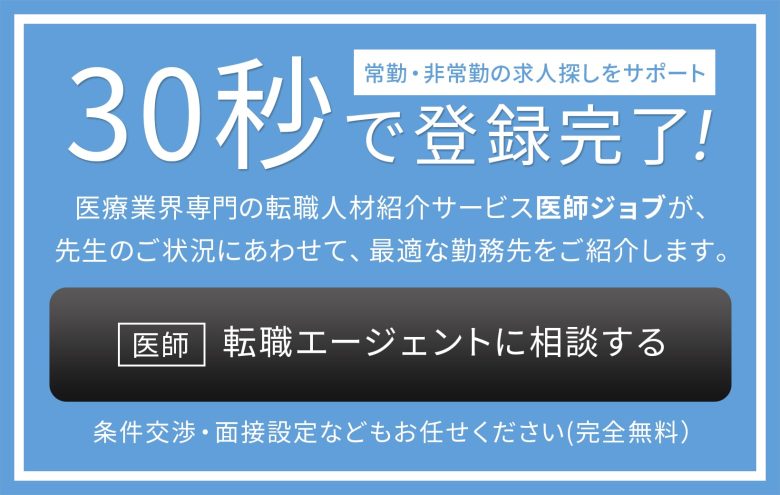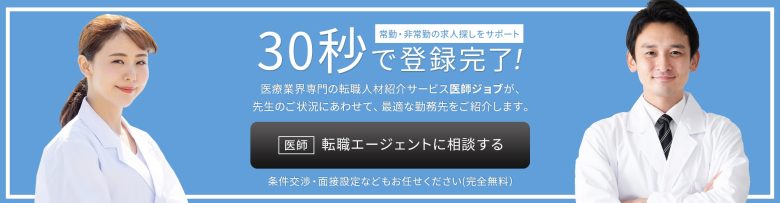┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
◇ 医師ジョブマガジン 2023.09.12号 ◇
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
4月から少子化対策の一環として、出産一時金が原則42万円から50万円に引き上げられたことはご存じでしょうか?
「出産一時金」とは子どもを出産したときに受け取ることができる一時金で、出産した子ども一人に対して支給されます。
健診や分娩費用など出産には費用がかかるため、経済的負担を減らすために設けられた少子化対策の一つです。
1994年に開始された制度で開始当初は30万円でしたが、その後時代の出産費用の実態に応じて増加し、2009年には42万円、2023年には50万円まで増額されました。
しかし今回の増額と同じくして、各医療機関・助産院が定める出産費用も値上げする現象が起きているようです。
厚生労働省が全国の医療機関や助産院にアンケートを実施した結果、出産一時金の引き上げの発表以降、出産費用を値上げした施設が回答した施設の26%程度あったそうです。
実際、今年の平均出産費用は去年より約2万円増の「平均50万3000円」となっています。
値上げに関して「便乗値上げ」という批判もありますが、もちろん正当な理由の場合もあります。
主に光熱費の上昇が言われますが、他にも医療機器や薬品の高騰も理由として挙げられています。
また、産院施設の集患の激化によるサービスの多様化も原因の一つでしょう。
実際のところ高度な医療を受けられる病院や、ブランド力が高い施設での出産など、付加価値のあるサービスを求める方が多いことは事実。
個室、豪華な入院食やエステなどのプラスアルファのプラン、無痛分娩の有無などにより、入院費を含む出産費用は自然と増加してしまいますよね。
言うまでもありませんが、出産一時金が増加しても出産費用が高騰してしまっては、少子化対策の効果が薄れてしまいます。
晩婚化や少子高齢化が深刻化するこの時代、出産に必要な費用が上がり続けることで、最初から出産を諦める人もいるかもしれません。
そうなれば、産婦人科や小児科がご専門の先生にとっても死活問題です。
とはいえ、政府も引き続き対策を進めています。
不妊治療への保険適用については2022年から開始され、今後も2024年4月から出産費用を「見える化」するため施策が検討されている最中。
今後もしばらくは出産費用への更なる施策など、引きつづき出産を後押しする対策が進められていくことでしょう。
※このコラムは2023年9月に配信した記事です