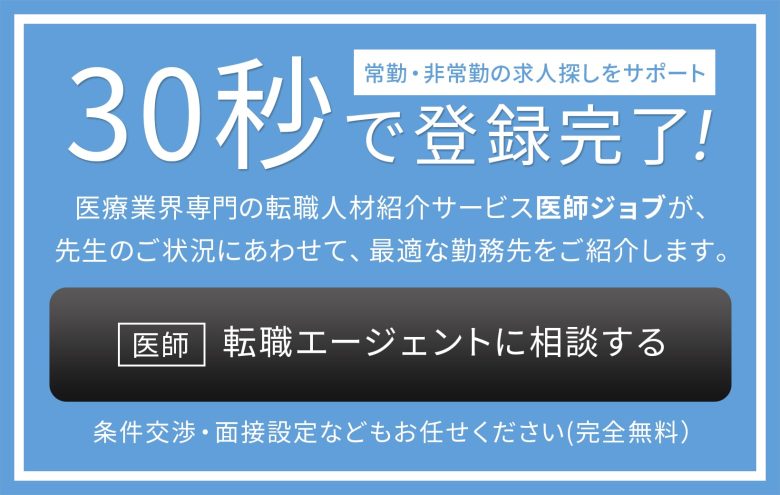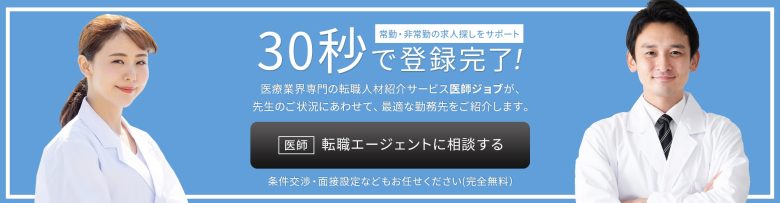┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
◇ 医師ジョブマガジン 2023.01.13号 ◇
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
人間、誰しもミスをするのはやはり避けたいもの。
しかしヒヤリ・ハットも含めて、基本的にミスは思い込みで起きることが多いため、一人で気づくことはなかなか難しいとされます。
医療現場では1つのミスが大きな医療事故に繋がることから、それを防ぐ目的でダブルチェックがよく行われます。
それは同職種だけでなく、職種を超えたダブルチェックも度々行われていますよね。
一方で、ダブルチェックに対して「手間ばかり増える」・「本当に有用か」と感じている方も少なくないでしょう。
確かに、チェック者が2人以上になると「甘くなる」とはよく言われます。
「●●さんがチェックしたなら多分大丈夫だろう」
こういった思い込みから、次のチェック者はどうしても手を抜いてしまいがちです。
というのも、これは1910年代から長く「リンゲルマン効果(社会的手抜き)」として語られる現象です。
「集団で1つの作業を行うと、1人で作業している時よりも、1人あたりの生産性が低下する現象」を指します。
1つの物事に関わる人数の増加に反比例して1人あたりの役割・責任感が分散されていくことから、「まあ●●さんがいるし、自分は適当でもいいか」となってしまうのです。
ちなみにリンゲルマンは綱引きなどの肉体的な作業でそれを実証しましたが、実のところ、仕事上の責任といった精神的な作業や会議などでも同じことが起きます。
というのも、これが意識的な行動ではなく、無意識下の行動であるためです。
じゃあその分自分が頑張ろうと思った先生もいらっしゃるかもしれませんが、そうするとチームは悪循環へと落ちていくこともわかっています。
リンゲルマン効果を放置してしまうと、物事に対して何もしない人とそれをカバーする人が常態化し、チームの崩壊を引き起こしかねません。
解消方法はいくつかありますが、やはり個人の責任範囲を細やかに限定し、その分責任から生じた結果(成果)を正当に評価することが解決策の一つと言えます。
もちろんミスをしないことが一番良いことではありますが、人間ですのでミスを完全になくすことは難しいでしょう。
しかし報連相・責任範囲がしっかりしていればミスをしても気づく心の余裕も持てるため、「ほど良い緊張感のある環境」に身を置くことができ、仕事のパフォーマンスも上がることでしょう。
時に、パフォーマンスを向上させたい場合には、職場の状況を俯瞰し、現在の自身の状況と照らし合わせることも有用です。
もし職場環境の改善に努めても改善が見込まれないなどがあれば、転職という切り札を切ることも視野に入れてみてください。
※このコラムは2023年1月に配信した記事です