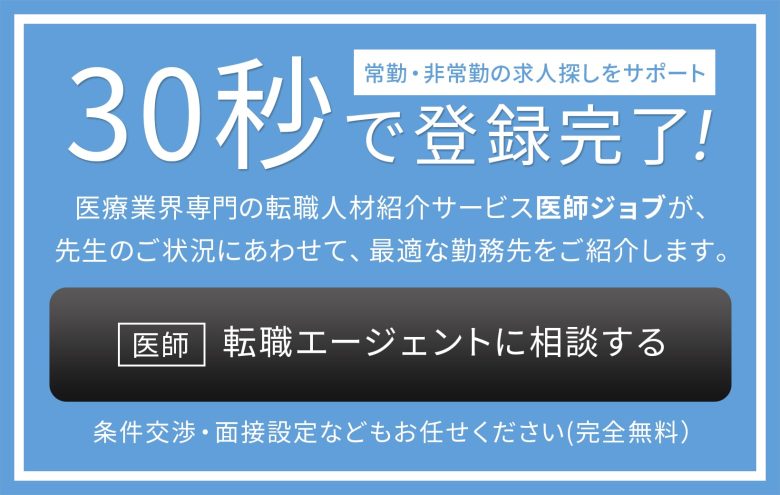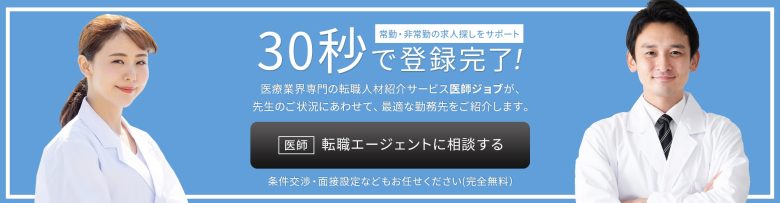2018年に医学部入試における女性差別の記事があり、かなり大きな問題となっておりました。
厚労省の調査では、女性の医師数は1990年あたりから少ないながらも右肩上がりで増えており、2018年度には2016年調査より女性は6.2%増加しています。
また、年代毎の性別割合では「29歳以下」の女性医師が35.9%と割合が最も高く、次点が「30~39歳」で女性医師31.2%となり、やはりと言うべきか、若い世代ほど割合が高い傾向にあります。
その若手医師からご転職のご相談をいただく際に、よくあるご質問の一つとして育児休業制度があります。
実際に制度は知っていても内容をご存じでない方も多いのではないかと思います。
育児休業制度とは、原則として「1歳に満たない子どもを養育する労働者が、会社に申し出ることで、養育する期間を休業できる、育児・介護休業法により定められた制度」です。
期間を定めて雇用される者は、次の2点いずれにも該当すれば育児休業を取得でき、最長2歳まで育児休業の再延長が可能です。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ただし、対象外とする労使協定がある場合に限り、以下の要件を満たす労働者は育児休業を取得できません。
・雇用された期間が1年未満
・1年(1歳以降の休業の場合は、6カ月)以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下
また育児休業は制定当時から男性も取得できることが注目されてきましたが、取得実態は女性の取得率に比べて男性は3%程度。
以前より微増していますが、やはり低水準となっています。
そこで行政では「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」という制度を新設し、男性が育児休業を取得することで女性の職場復帰を助けることを推奨しています。
ちなみにパパ休暇は「子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度」のこと。
「子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること」かつ「子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること」が取得要件です。
詳細は厚労省のページに載っておりますが、転職中の方でお話が気になる方は是非ご相談ください。
このような福利厚生面から考えた転職のご支援も積極的に行っております。
些細なことでも気になることをご相談いただけることで、よりご希望に近しい環境の求人をご紹介できるかもしれません。
気軽にご相談くださいませ。