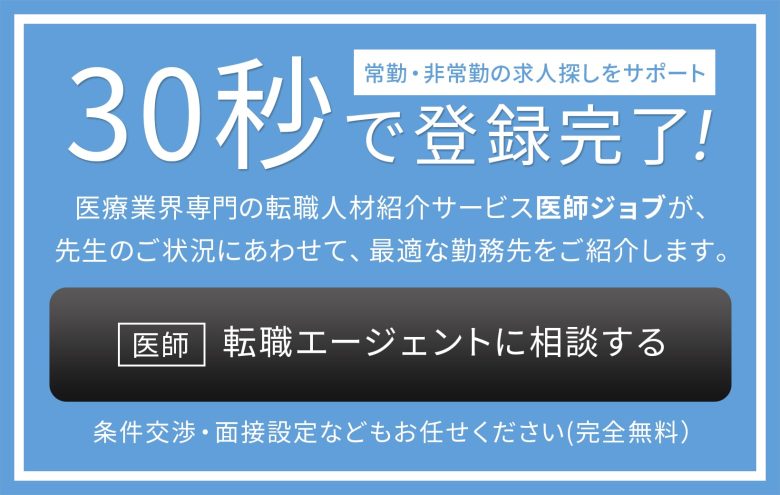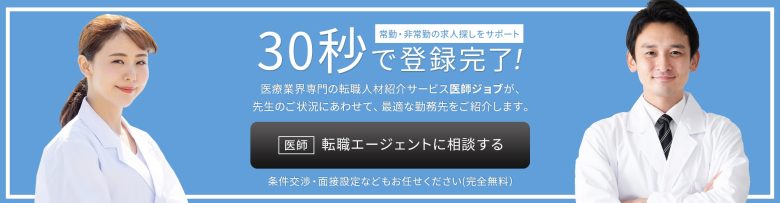最近、体感で少し大きいと感じる地震発生回数が増えていて心配ですよね・・・。
そこで本日は災害時医療の中心を担っている「災害拠点病院」についてお話します。
災害拠点病院
災害拠点病院とは、“災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院”を言います。
英語にすると「Disaster base hospital」と訳されることが多いようです。
災害発生時に被災地内の傷病者の受入れ機能を有することに加えて、傷病者の広域搬送への対応・医療救護チームの派遣・地域医療機関への応急用資器材の貸し出しなど、災害時の初期救急医療体制を整えるための様々な機能を有しています。
2021年4月1日時点で、日本全国で759施設が指定されており、下記2種類に分類されています。
・基幹災害拠点センター…各都道府県に1か所以上
・地域災害拠点センター…2次医療圏に1か所以上
災害医療の歴史
そもそも、災害拠点病院が設置されたのは1995年の阪神・淡路大震災がきっかけでした。
多くの犠牲を生んだこの大震災は、災害医療に関する救急医療、建築、設備や通信機器など多くの課題を明らかにしました。
さらに2011年の東日本大震災も大きな転機となりました。
地震だけでなく津波も含めた複合災害だったことで、災害医療=地震前提の災害医療計画では対応が難しい場面が出てきました。
実際、耐震構造などで建物の倒壊自体は防ぐことができたものの、津波の浸水などで設備が使いものにならない災害拠点病院もありました。
また運ばれてくる患者の状況が異なっていたことも大きいと言えます。
外傷や挫滅症候群といった負傷者の方が多かった阪神・淡路大震災と違い、東日本大震災では津波による死者や慢性疾患の継続治療が難しくなり搬送された患者が多かったそうです。
つまり、地震発生直後に運ばれてきた患者よりも、その後に運ばれてきたご遺体や搬送された患者の方が多い状況となりました。
そのため東日本大震災後には、災害医療計画や災害拠点病院の指定要件に対しての大幅な見直しが図られました。
その後も熊本地震など災害における事例などが報告される度、より事例に沿った具体的な災害時医療の想定の上で計画の策定を行うなど様々な進歩を遂げています。
災害拠点病院の要件
DMATなどに所属されている先生方などはご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、災害拠点病院の指定を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
また、指定に関しては各都道府県が行っており、厚生労働省の指定要件に合致しているかを毎年確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定は解除されるなど、厳格に管理されています。
運営体制
- 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。
- 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。
※「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合、重症傷病者の搬送先であること。被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。 - 災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制・他の医療機関のDMATの受入体制があること。
- 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。
- 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。
- 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。
- 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、医療関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。
- 災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。
- ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。
施設環境
- 病棟(病室、ICU等)、診療棟(診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設置すること。
※災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常時の2倍、外来患者については通常時の5倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 - 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。
- 通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等、3日分程度の備蓄燃料を確保すること。
※自家発電機等の燃料として都市ガスを使用する場合は、非常時に切替え可能な他の電力系統等を有しておくこと。 - 災害時に少なくとも3日分の病院の機能を維持するための水を確保(少なくとも3日分の容量の受水槽を保有又は停電時にも使用可能な地下水利用設備(井戸設備を含む。)を整備)
保有設備・物品など
- 衛星電話・衛星回線インターネット環境を整備。また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。
- 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加・災害時情報入力体制(担当者・入力操作などの研修含む)を整えておくこと。
- 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備
- 患者の多数発生時用の簡易ベッド
- 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等
- トリアージ・タッグ(識別票)
搬送体制
- 原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保、患者搬送用の緊急車輌を有すること。
- DMATや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。
- 車輌には応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。
基幹災害拠点病院への要件
地域災害拠点病院よりもさらに厳しく、上記の要件に加えて下記の要件も課されています。
- 複数のDMATを保有していること。
- 救命救急センターであること。
- 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。
- 病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有すること。
- 病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。
参考:「災害拠点病院指定要件の一部改正について」(令和元年7月17日付け医政発0717第8号厚生労働省医政局長通知)
災害医療における課題
災害拠点病院は、被災地での初期医療体制を整えるための重要な存在です。
しかしながら、先生方がお勤めになる医療機関が災害拠点病院でなかったとしても、かかりつけ患者や地域住民がそうであるかどうかを必ずしも理解しているかというと怪しいですよね。
災害医療においては、「3T」・「3Ts」とも呼ばれる「Triage(トリアージ)」、「Treatment(治療)」、「Transportation(搬送)」が鍵となってくることは言うまでもありません。
しかし阪神・淡路大震災の際には、重症患者を地域住民自ら近くの病院へ搬送した事例も多かったという報告もあります。
(もちろん建物の倒壊などで救急車が通れなかったため、自力で搬送するしかなかったという事例も考慮せねばなりません。)
人員も含めて限られた物資で行う診療の中、すぐに診ることのできなかった患者が居たことも事実です。
そのため、「運ばれてきた患者の中に救えた命があったのでは」という議論が起こりました。
広域災害救急医療情報システム(EMIS)の活用
先述の通り、阪神・淡路大震災においては医療機関同士の共有方法がなく(関係各所からの電話などが中心だったようです)、災害時には医療の不均衡によって医療機関ごとの診療比重も異なっていたことが問題視されました。
それらを解消することも目的として、広域災害救急医療情報システム(EMIS)が生まれ、運用されてきました。
しかし電力が制限される中でEMISが使えるかという疑問や、果たして有事の際に誰が入力できるのかという疑問が浮かびます。
東日本大震災では、やはりEMISに入力できたところは少なかったそうで、行政の代行入力なども行っていたようです。
ただし当時被災県の中では行政が加入していなかったところもあったために、すべて病院任せになっていて更新できた例が少なかったという報告されていました。
さらに当時はDMATがインターネット接続が可能な衛星環境を有していなかった例も見受けられ、DMATの入力もできなかった例もあったようです。
システムを活かすためには、こういったことに対しての備えなども必要だと言えます。
事業継続計画(BCP)の策定
厚生労働省は都道府県に対して「事業継続計画(BCP)」の策定を勧めるよう通達を出し、都道府県もそれに従い、策定におけるマニュアルなどを公開しています。
事業継続計画(BCP)は災害などが発生した際、損害を最小限に抑えて限られた中で診療を行いつつ、復旧を図るための計画です。
先述のEMISの入力においてもBCPで定めておくと有事において行動しやすいですよね。
BCPの存在は、先に欧米諸国をはじめとする海外で広まりましたが、そのきっかけはアメリカ同時多発テロ事件でした。
その後、日本でも官公庁が身近な災害などを想定してマニュアルなどを進めていましたが、やはり国内で本格的に動く契機となったのは東日本大震災です。
この言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんが、実際、事業継続計画(BCP)に対する医療機関の認知度は低い状況にあります。
2018年12月に行われた厚生労働省の病院の業務継続計画(BCP)策定状況調査の結果によれば、医療機関の回答は以下の通りです。
| 回答のあった病院数 | 内、策定予定はないと回答した数 | 策定予定のない病院割合 | |
| 全医療機関 | 7,294 | 5,468 | 75.0% |
| 災害拠点病院 | 690 | 199 | 28.8% |
回答が返ってきた7,294病院の内、5,468病院(75.0%)が事業継続計画(BCP)の策定予定はないと回答しています。
では災害拠点病院ではどうかといえば、回答のあった690病院の内、199病院が策定予定はない(28.8%)という回答でした。
年度も進んでいますので実数とは乖離しますが、それでも決して少ない数字ではありません。
元々DMATも災害発生から48時間以内を目安に活動しており、概ね100時間以内には後方支援もしっかりするということから活動を終了し、他(医療機関やJMATなど)に引き継ぐ方針になっています。
そして何より悪路などを想定すると発生直後すぐに来るということもありません。
いつ起こるかわからない災害に対しての備えとしてやはり必要であると言えます。
人為災害への対処
また災害とひとくくりにしていても、そこには地震・水害・噴火・土砂災害といった自然災害だけでなく、航空機・列車事故やテロ事件といった人為災害も含まれます。
日本では前者の制度は整えられてきましたが、後者の発生事例が少ないこともあり、まだまだ追い付いているとは言い難い現実があります。
DMATが発足して以降、人為災害に初めて出動したのは、JR福知山線脱線事故です。
事故発生後の第一報においては被害想定が実際よりも過少だったこともあり、DMATなども含めて現場の医療従事者が本当に充足しはじめたのは事故発生から4時間後の午後12時頃となりました。
充足するまでは、一早く近隣住民などが一番最初に現場入りした医療チームと連携し、死傷者の救助活動や搬送をはじめていた状況だったようです。
この点において、災害医学会はDMAT 標準テキストの中で「午後12時頃まで現場において十分なTreatment(治療)がなされていなかった」と問題点を指摘しています。
また、圧迫で動けなかった生存者が3名発見された午後4時頃には、1病院を除き医療チームが撤収してしまったあとであったことも問題点として挙げ、現場の指揮・統制が十全でなかった点も指摘しています。
母体が異なるチームで指揮・統制を行う際に必要なことは、やはり情報共有です。
しっかりとした現場内外での情報伝達は、やはり課題のひとつとして挙げられそうです。
ただし、JR福知山線脱線事故は、阪神・淡路大震災を経験した兵庫県で起こった事故です。
近隣住民の協力を得られた理由や災害拠点病院が大いに役立った理由でもあり、また第一報こそ想定が過少でしたがEMISが役に立ったことはDMAT標準テキストでも触れられていました。
他にも、秋葉原無差別殺傷事件では全国に先駆けて設置された東京DMAT小脳長などもから連携して活動し、記憶に新しいところでは大阪における心療内科クリニックへの放火でもDMATが出動しました。
幅広い災害に対してどこまで想定し、実際にどこまで対応できるか。
新しく災害が起こる度に経験が積まれていくことになりますが、一方で課題として見えてくるものもあるので、常に知識・情報を更新していく必要性があります。
最後に
人為災害に関しては起こらないことが何よりではありますが、今この時も自然災害であれば起こり得ます。
その際、ご勤務先の病院が災害拠点病院の指定を受けていれば、有事の際にはその役割を担うことになります。
そうでなくとも、後方支援として何かしらの形で災害時の医療に協力する必要が出てくる可能性もあります。
転職活動時には学会認定などの他にも、その医療機関がどういった指定を受けているかにも目を通しておくといいかもしれません。