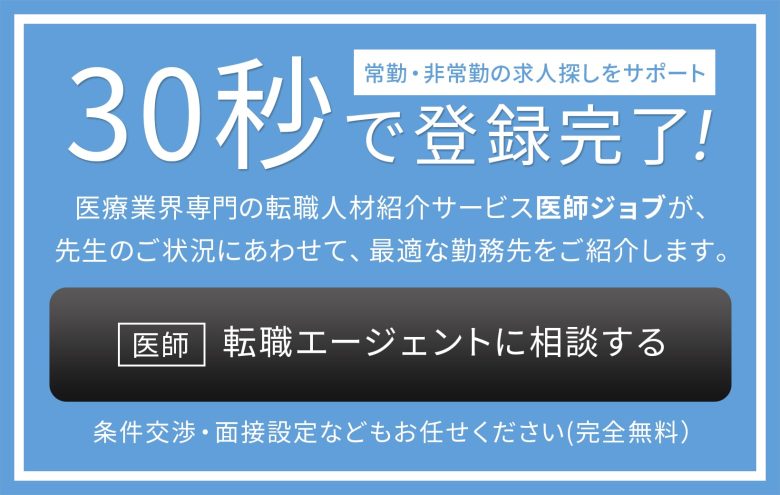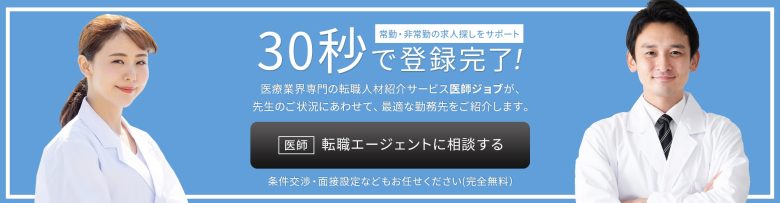医師ジョブに寄せられるご相談の中でも、断トツに多いのが「業務が負担になっているので転職したい」という趣旨のご相談です。
ご相談いただく方の年齢層も若手医師からベテラン医師まで幅広く、多くの医師が現状の業務負担に頭を悩ませ、転職を考えている状況です。
もちろん、そこには業務負担以外の理由もあるとは思いますが、辞めたいと感じる原因として挙げられがちなところを見ると、やはり根本的に改善が必要なことは間違いありません。
実際、以前から引き続きこちらでも解説していますが、一般的に医師の労働時間は全ての職種の中でもトップクラスといわれています。
多様性が進んでいますが、それは働き方にとっても同じこと。多様な働き方を選べる社会にするため、2019年4月から政府主導の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(通称:働き方改革関連法)」が施行されています。ただし医師の場[…]
今回は上記に関連して、医師の業務負担の実態と負担軽減への取り組みに関して、解説してまいります。
働く上で疲労を感じる業務
独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った「勤務医の就労実態と意識に関する調査」。
これによると、医師の1週間あたりの労働時間は平均で46.6時間、1週間あたりの全労働時間については約4割が「60時間以上」と回答しています。
また同調査では「医師として働く上で疲労を感じるもの」という質問項目も設けており、上位5位は以下の通りです。
| 業務 | 比率 | |
| 1位 | 当直(宿直及び日直) | 61.6% |
| 2位 | 長時間労働(当直以外) | 50.6% |
| 3位 | 患者(およびその家族)の理不尽な要求 | 49.0% |
| 4位 | 病院内の診察外業務(院内委員会活動・会議等) | 46.5% |
| 5位 | レセプト以外の書類作成 | 44.8% |
引用:独立行政法人労働政策研究・研修機構「勤務医の就労実態と意識に関する調査(2012年)」-pdf形式
こちらは少し古く2012年の調査ですが、現状の先生方と比べてどうでしょうか。
実際に当直がご負担になっているというお話はよくお聞きするところで、女性医師などは特にご都合から当直勤務などが難しく、なかなかキャリアに復帰できないという例も見られます。
病院側の改善への取り組み
では、実際、病院側は勤務医に対してどのような取り組みを行っているのでしょうか。
令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査に「医師の負担軽減策として実施している取組」として医療機関が回答したものがあります。
実施している医師の負担軽減策で最も多かったものは「医師事務作業補助者の外来への配置」で66.6%となりました。
その後は、「院内保育所の設置(50.7%)」、「医師の増員(46.3%)」、「当直翌日の業務内容の軽減(当直翌日の休日を含む)(44.6%)」と続きました。
とはいえ、こちらの回答方法は複数回答のため、1医療機関がいくつもの取り組みを掲げていることになります。
また、新型コロナウィルス感染症対応病院とも被る「地域医療体制確保加算届出病院」だけに絞って見ると、中身こそ同じものの、実施割合の比率が高くなっていました。
「医師事務作業補助者の外来への配置(87.9 %)」、「院内保育所の設置(79.9%)」、「当直翌日の業務内容の軽減(当直翌日の休日を含む)(66.7%)」という結果になりました。
- 地域医療体制確保加算届出病院
- 【 名称・点数 】
地域医療体制確保加算(520点)
【 施設基準 】
救急医療に係る実績として救急車・ドクターヘリなどによる救急搬送が年間2,000件以上(1月~12月)あること。
病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整えること。
など
【 ちなみに… 】
2020年10月時点となりますが、200床~399床の医療機関の76.6%、400床以上の医療機関で97.4%がこの加算の届出を行っています。
また、新型コロナウィルス感染症専用病棟を設定する重点医療機関の88.3%もこちらを届け出ています。
そのため、加算を届け出ている医療機関において、新型コロナウイルス感染症の影響が心配されていたため、今回この加算に着目した統計が取られました。
また、2020年4月~11月1日間、一度でも医療提供状況に変化があったか?という質問に対して、上記を届け出ている病院は入院や手術で制限を設けた割合が高かったという結果も見られます。
実際のところ、改めて統計上でも新型コロナウィルス感染症の影響度は大きかったと示されることになりました。
医師事務作業補助者の外来への配置
医師事務作業補助者とは?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、2008年に医師の働き方改革を推進すべく導入された職種です。
ご勤務する医療機関によっては「医療クラーク」とも呼ばれているかもしれません。
医師事務作業補助者の業務は、ご存じかもしれませんが文書の代行作成・データの入力だけでなく、多岐に渡ります。
- 各種診断書や退院サマリー等の文書代行作成
- 診療情報提供書(紹介状、返書等)の代行作成
- 診療録の代行記載、各種オーダー
- 臨床データベースへの入力(NCDなど)
- 学会資料収集・作成、文献検索
- 患者・家族説明文書の作成、手術予定の管理
- 院内会議資料作成 …など
タスクシフティングの話とも関連しますが、医師の業務負担としても挙げられがちな書類作成などの業務を担う存在として期待されています。
ただし一方で、個人のスキル差があることや、医師事務作業補助者としてのキャリアパスが不透明なこと、さらに人員の確保が難しい現状などなど、多くの課題が残ったままです。
しかし、病院側からすれば、この医師事務作業補助者の話は前向きに検討しているところも少なくありません。
というのも、勤務医負担軽減計画を策定した上で、届出区分の病床数ごとに1名以上専従の医師事務作業補助者の配置などを行うことで、「医師事務作業補助体制加算1・2」が申請できるためです。
- 医師事務作業補助体制加算
- 【 点数 】
許可病床数に対する医師事務作業補助者の配置人員で変動。配置 加算1 加算2 15対1 970点 910点 20対1 758点 710点 25対1 630点 590点 30対1 545点 510点 40対1 455点 430点 50対1 375点 355点 75対1 295点 280点 100対1 248点 238点 【 施設基準 】
医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制の整備。
病床ごとに医師の指示で事務作業の補助を行う専従の者(医師事務作業補助者)の配置。
医療機関で策定した勤務医負担軽減策により、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者を置いていること。
などなど
【 加算1・加算2の違い 】
延べ勤務時間数の8割以上の時間で医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われている場合に加算1、それ以外の場合には加算2となります。
まだこの加算を届け出ている医療機関は多くありませんが、決して少ないということでもありません。
算定可能な対象医療機関が2020年度の診療報酬改定により拡大されたことも一因です。
コロナ禍でなかなか動きが難しいところですが、国が進めている医師の働き方改革とあわせて、今後も医師事務作業補助者の配置は進んでいくと考えられます。
院内保育所の設置
「平成29年医療施設(静態・動態)調査」によれば、病院における院内保育の実施状況は全病院のおよそ40%です。
| 病院総数 | 院内保育有 | うち、夜間保育有 | うち、病児保育有 | |
| 2011年 | 8,605 | 3,259(37.9%) | 1,688(51.8%) | 557(17.1%) |
| 2017年 | 8,412 | 3,685(43.8%) | 1,947(52.8%) | 783(21.2%) |
引用:平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況
参考:厚生労働省通知「院内保育等の推進について」(令和元年7月1日付)-pdf形式
2011年に比べれば増加傾向にあるものの、それでも高い比率とは言い難い状況です。
ただ、2015年から病院内における保育所に対する支援策がはじまり、2018年には幼児教育・保育(3~5歳)の無償化もはじまったため、背景としては設置が進んでいます。
特に2015年の支援策に関しては、明確に医療従事者の確保に関する事業として病院内保育所の運営・施設整備への補助を行うという形になっています。
もっとわかりやすく記載すると、看護師だけでなく女性医師に対する就労支援という側面もあり、預かりの定員数や保育所の人員の確保なども課題とされてきました。
その点を解決するため、企業などが主体となって開設される企業主導型保育事業も同時に進められました。
整備費、運営費の助成制度も設けられ、また特に企業の参入によって現状では数が少ない病児保育が開始されるのではと期待されました。
と、つらつらと書いてきましたが、国も助成制度を設けるなどして、この取り組みに対しては手厚く支援しています。
では、そんな中で実際の医師の利用率はどうかというかと、同調査によれば2017年に院内保育を行う3,685病院のうち、医師・歯科医師の利用があると回答したのは2,628医療施設(71.3%)。
もちろんこの数には歯科医師のみが利用している施設も入るため、全部が全部医師の利用があるかというとそうではありません。
また、医師は圧倒的に男性比率が高い職種でもあるため、そもそも病院へ就労する女性医師もそこまで多くないことも一因かもしれませんね。
当直の負担軽減
厚生労働省の「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」によれば、常勤医師の当直の平均回数は中央値が月2.0回、平均値が月2.3回となりました。
▼ 1 か月間の 常勤医師1 人あたり平均当直回数(病床規模別)
| 有効回答数 | 平均値 | 中央値 | |
| 99床以下 | 71施設 | 月2.7回 | 月3.0回 |
| 100~199床 | 111施設 | 月2.4回 | 月2.0回 |
| 200~399床 | 97施設 | 月2.0回 | 月2.0回 |
| 400床以上 | 67施設 | 月2.0回 | 月2.0回 |
| 全体 | 355施設 | 月2.3回 | 月2.0回 |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査-医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査(2020年)」-pdf形式
長時間労働に関しては先述の関連記事で解説済みですが、当直に関しては病床数が少ない病院ほど多くなる傾向にあるようです。
原因としては、やはり医師の人員数の問題なども大きいと言えます。
一方、救急などが多い医療機関の場合、大学などの医局や非常勤・スポットによる外勤医師の当直勤務が行われているケースも見受けられます。
常勤医の負担を減らすため、外部の力を借りて運用していることも病床数の多い医療機関における常勤医の当直回数が少ない一因かもしれません。
また連続しての当直勤務は、同調査によれば平均値月0.4回(2020年10月調査)でしたが、近年では少しずつ連続勤務が見直されている傾向にあります。
もちろん、人員の急な欠員などで当直せざるを得ない場面も有り得るため、0回とはいきませんが、それでも以前に比べれば減少傾向にあると言って良いでしょう。
ただし「月2回の当直も負担が大きい」というご意見もあるかと思いますので、この辺りはもう少し議論されるべき問題と言えます。
昨今、働き方改革が進んでいますが、特に活発に議論されているのが「長時間の時間外労働」です。しかしながら医師の長時間にわたる時間外労働は他の職種に比べて若干特殊です。そして、その一因として挙げられるのが、医師特有の「応招義務(※)[…]
医師の負担軽減策への実感
では、実際上記の取り組みを医療機関が行う中、医師はどう感じているのでしょうか。
医師が特に効果のある取り組みとして挙げていたのは、「99 床以下」で最も多かったものは「医師の増員」(27.4%)です。
ちなみに100 床以上の病棟で最も多かったものは「医師事務作業補助者の外来への配置・増員」で、「100~199 床」(27.1%)、「200~399 床」(35.4%)、「400 床以上」(42.3%)となりました。
各病床規模ごとに効果のある取り組みとして挙げたトップ5を挙げておくと以下のようになります。
| 99床以下 | 100~199床 | 200~399床 | 400床以上 | |
| 1位 | 医師の増員 27.4% | 医師事務作業補助者の外来への配置・増員 27.1% | 医師事務作業補助者の外来への配置・増員 35.4% | 医師事務作業補助者の外来への配置・増員 42.3% |
| 2位 | 医師事務作業補助者の外来への配置・増員 23.3% | 医師の増員 25.8% | 医師の増員 30.0% | 医師の増員 37.4% |
| 3位 | 複数主治医制の実施 18.5% | 医師事務作業補助者の病棟への配置・増員 22.5% | 当直翌日の業務内容の軽減(当直翌日の休日を含む) 22.6% | 複数主治医制の実施 31.9% |
| 4位 | 当直翌日の業務内容の軽減(当直翌日の休日を含む) 13.0% | 薬剤師による投薬に係る入院患者への説明 18.8% | 複数主治医制の実施 薬剤師による投薬に係る入院患者への説明 ともに21.0% | 当直翌日の業務内容の軽減(当直翌日の休日を含む) 30.8% |
| 5位 | 医師業務の看護師(医師業務の特定行為研修修了者を除く)との分担 10.3% | 複数主治医制の実施 15.8% | 医師事務作業補助者の病棟への配置・増員 23.3% |
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査-医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査(2020年)」-pdf形式
※ 注:1人3つまで回答
なお、各業務の負担感として同調査で医師が「負担が大きい」としたのは、「診断書、診療記録及び処方箋の記載」・「主治医意見書の記載」(ともに35.0%)だったというデータもあります。
一方で医師事務作業補助者の導入により改善・軽減が見られた医師業務内容で最も多く挙げられていた選択肢が、「診断書や紹介状、意見書、処方箋、各種保険の証明書などの作成代行」(87.8%)だったことは併記しておかなければならないでしょう。
もちろん、医師事務作業補助者がすべてではありませんが、実際に負担であると思っている書類などの業務を代行してくれれば負担は減りますよね。
統計では医師事務作業補助者の作成代行により平均値で月4時間ほど改善されたという回答もありました。
とはいえ、この回答には当直業務の選択肢はなく、当直が一番負担が大きいと感じている先生方の多くからすれば、それだけでは足りないと感じるのではないでしょうか。
国はこうした状況を改善するために医師の「働き方改革」を進め、医師の労働時間の短縮などの労働環境の改善を目指しています。
今後も厚生労働省は引き続き調査などを続けていき、タスク・シフティングの効果などもしっかりと問うと考えられます。
時間外労働の規制などがどこまでうまく作用するのか、当直・オンコールの負担がどこまで軽減できるか、医師はどこまで増加できるか……未だ課題は山積みです。
医師の重い業務負担に対して、しっかりとした解決策が求められています。
最後に
今も勤務状況に悩まれている先生や、医師不足の中で心身ともに休めず患者様とじっくりと向き合えない環境で働いている先生も多くいらっしゃると思います。
さらに睡眠不足から集中力が低下し、普段なら考えられないようなケアレスミスや忙しさによる余裕のなさから患者様との接し方にも影響が出てしまうかもしれません。
働く上で疲労やストレスを感じるものは人それぞれかと思いますが、心身ともに健康な状態で働くことは、先生にとっても患者様にとってもベストな選択肢の一つかと思います。
現在医師の転職では医局・知人からの紹介だけでなく、転職会社を利用して自力で転職する方も増えています。
転職するか迷っているが、働き方に悩んでいる、という方もまずはクラシスの医師ジョブにご相談ください。