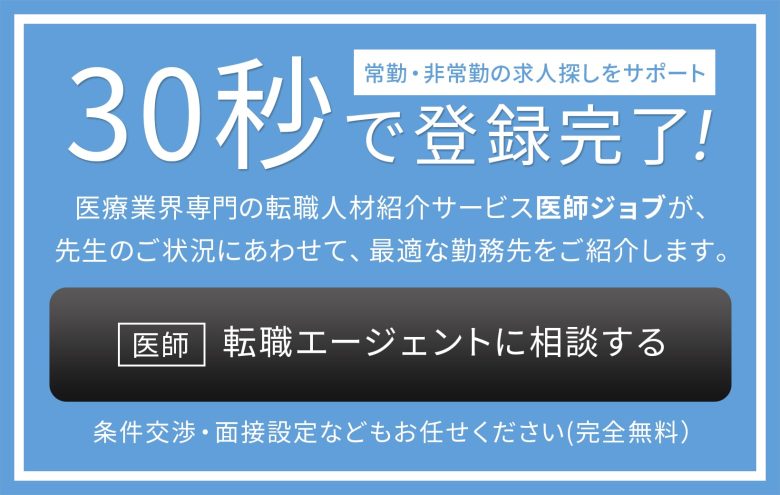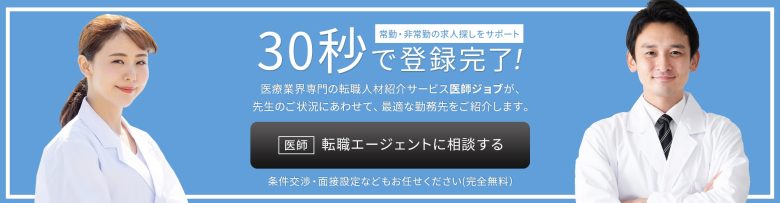医師や歯科医師が何らかの問題を起こした場合、行政処分を受ける可能性があります。
苦労して医師になったからには、医業停止や医師免許取消などの最悪の事態は避けたいものですよね。もちろん、自ら進んで問題を起こそうと考えるケースは滅多にないとは思いますが、医療事故を起こしてしまった、交通事故を起こしてしまったなど、望まずとも行政処分の対象となってしまう可能性はゼロではありません。実際に、毎年行政処分を受ける医師がいるのもまた事実です。
そこで今回は、医師の行政処分に関してその種類や内容、そして行政処分を受けることによって生じる悪影響など、知っておいて損はない医師の行政処分について詳しく解説いたします。
医師の行政処分とは?
一口に行政処分と言っても、その内容は様々です。こちらでは、医師の行政処分に関する基礎知識を解説いたします。
そもそも行政処分とは?
「行政処分」とは、行政が法律の規定に従って、国民の権利や義務に対して直接影響を及ぼす一方的な行為のことを指します。似ている言葉に「行政指導」がありますが、行政指導は非権力的な「お願い」であり、従うかどうかは任意です。一方、行政処分は権力的な「命令」であり、強制力が発生します。行政処分の内容には様々なものがありますが、一般的な例としては運転免許停止や営業停止などが挙げられます。
医師の行政処分はどのように下される?
医師の資格に関する行政処分は、厚生労働大臣が医道審議会の意見に基づいてその処分内容を決定します。処分対象となる医師の行為や過失の軽重を踏まえたうえで、職業倫理や法律に反すると判断された場合、行政処分が下されることになります。
医師法第7条によると、以下に当てはまる医師は行政処分の対象となります。
- 心身の障害により医師の業務を適正に遂行できない者
- 麻薬・大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 医事に関し犯罪又は不正行為のあった者
- 医師としての品位を損するような行為のあった者
出典:医師法 | e-Gov法令検索(第七条・第四条)
現状、行政処分の大半は「罰金以上の刑に処せられた者」に対して下されています。しかし、それ以外のケースが全くないわけではありません。
医道審議会は、行政処分の考え方について以下のように述べています。
国民の医療に対する信頼確保に資するため、刑事事件とならなかった医療過誤についても、医療を提供する体制や行為時点における医療の水準などに照らして、明白な注意義務違反が認められる場合などについては、処分の対象として取り扱うものとし、具体的な運用方法やその改善方策について、今後早急に検討を加えることとする。
実際に、医療ミスを繰り返した医師が刑事罰の確定を待たずに「医事に関し犯罪又は不正行為のあった者」として処分されたケースもあり、必ずしも刑事罰が確定しなければ行政処分が下されないというわけではありません。
医師の行政処分は3種類
医師の行政処分には、戒告・医業停止・免許取消の3種類があります。こちらでは、それぞれの処分内容について解説いたします。
| 医師の行政処分の種類 | 内容 |
| 戒告 | 違法行為や不当行為を戒める処分。 医師としての活動を制限されることはなく、いわゆる「厳重注意」にあたる。 |
| 医業停止 | 医業に携わることを一定期間禁止する処分。 停止期間は3年以内。 |
| 免許取消 | 医師免許を取り消す処分。 資格剥奪の重い処分だが、要件を満たせば再免許の申請が可能。 |
戒告
戒告は、行政処分の対象となる不当・違法行為を行った医師に対して再発防止のために戒める処分です。医師に対する行政処分のなかでは最も軽い処分であり、医師としての活動を制限されることはありません。
しかし、戒告処分であっても、行政処分を受けた場合は「再教育研修」を命じられる場合があります。再教育研修とは倫理保持・知識・技能に関する研修で、研修形態は処分の程度に応じて決まります。戒告処分の場合は団体研修を1日受ける必要があり、修了しなかった場合、法律に基づいて資格制限や罰金といったペナルティを受けることになります。
医業停止
医業停止は、一定の期間、医師として医業に携わることを禁止される処分です。期間は3年以内で定められ、停止期間を過ぎればまた医業を行うことが可能になります。
医業停止処分に反して医業を行った場合、対象者は懲役や罰金の対象となります。病院内での医業以外の業務(事務作業・受付など)に携わることは可能ですが、医業を行っていると誤解されないよう注意が必要です。
また、医業停止処分を受けると、戒告処分の場合と同様に再教育研修を命じられる場合があります。研修内容は医業停止を受けた理由や医業停止の期間に応じて変わりますが、基本的に団体研修に加えて課題学習や個別研修などが課されます。研修を修了しなかった場合にペナルティを受けるのは前述の通りです。
免許取消
免許取消は、医師の免許が取り消される処分です。免許そのものを失うので、時間経過で状況が回復することはありません。基本的に永久剥奪となり、医師としての活動がその後一切出来なくなる最も重い処分です。
ただし、一定の要件を満たせば再免許の申請をすることが可能です。しかし、免許取消になると待機期間(欠格期間)が発生するので、その期間中は再免許の申請は出来ません。刑事罰を受けた場合、待機期間とは別に「免許取消の理由となった事由に該当しなくなった」といえるまでの期間も必要となり、その期間は最低5年~最長10年になります。また、再免許を申請するには再教育研修も受ける必要があります。
刑事罰によって免許取消となった場合、再申請の要件を満たすだけでも相当な期間を要します。加えて、再免許の可否は厚生労働大臣の裁量によって決まるため、申請したからといって必ず免許を交付してもらえるわけではありません。再免許を受けるためには、要件を満たしたと主張するだけでなく、しっかり更生していることを示したり、取消事由が悪質でないことの裏付け資料を用意したりと、再交付が不相当と判断されないよう積極的に主張していく必要があります。
医師の行政処分によって生じる悪影響
医師が行政処分を受けた場合、その後の医師生活に悪影響を及ぼすことは想像に難くないでしょう。こちらでは、医師が行政処分を受けることでどのような影響が生じるのかを解説いたします。
社会的信用が低下する
行政処分は、基本的に不当・違反行為を行った医師に下されます。そのため、内容によっては社会的信用が低下する恐れがあります。勤務医であれば、退職を迫られたり再就職が難しくなったり、管理者・開設者・法人理事などであれば、経営状況が悪化したりなどの問題につながる可能性もあります。また、同業の他の医師からの目も厳しいものになるでしょう。
収入が途絶える
医業停止や免許取消の処分を下された場合、医師として活動出来ない期間が発生します。その期間中は当然ながら医業に携われないので、医師としての収入はゼロになってしまいます。また、自身の収入の問題だけでなく、クリニックを経営している場合などは家賃やテナント料、スタッフの給与を支払えなくなるといった二次的な問題に発展する可能性もあります。
手間がかかる
再教育研修や再免許の申請など、医師が行政処分を受けた場合、復活するまでには何かと時間と手間がかかります。行政処分に不服がある場合には審査請求や取消訴訟も可能ですが、手続きが煩雑であることに加え、審理が終わるまでは当該処分の効力は停止されません。暫定的に処分の効力を停止させるためにも別の手続きが必要になったりと、煩わしく感じられることも多いでしょう。弁護士などの専門家を頼るにしても、短期間で様々な問題に向き合う覚悟が必要になります。
まとめ
今回は、医師の行政処分について詳しく解説いたしました。
医師の行政処分には戒告・医業停止・免許取消の3種類があり、その処分は医道審議会の意見に基づき厚生労働大臣によって下されます。処分内容によっては今後一切の医師活動が出来なくなるケースもあり、たとえ医師免許取消に至らなくとも、行政処分を受けるということは社会的信用の低下をはじめとした様々な悪影響をもたらします。再起の道が全くないわけではありませんが、道のりは険しく、再就職・転職などもかなりハードルが高くなることは覚悟しなければなりません。
これまでの医師としてのキャリアをふいにしないためにも、行政処分なんて自分には無縁なこととは思わずに、常に医師としての自覚を持って行動することが肝心になります。