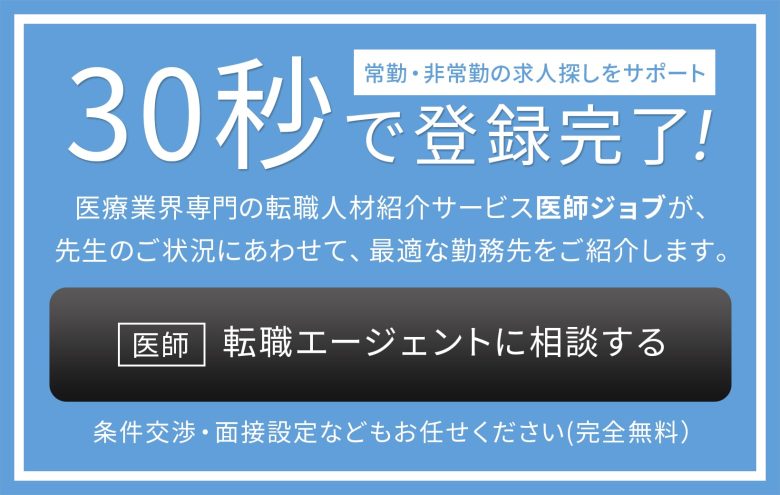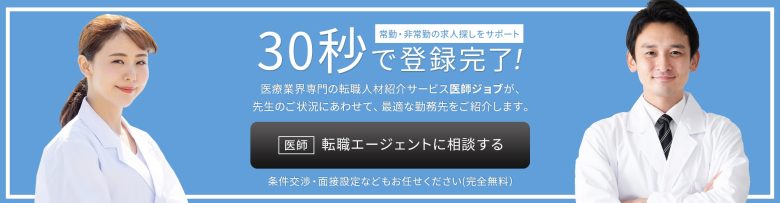一般的に医師というと、患者さんの診療に直接携わる「臨床医」のイメージが強いでしょう。
医学生の進路としても、将来は臨床に携わりたいと考える人が圧倒的に多いです。しかし、医師のキャリアプランには臨床医のほか、「研究医」として働く選択肢もあります。
研究医は近年なり手が不足しているものの、臨床医と同様に医療を支えるために必要不可欠な存在です。ただ、具体的な働き方がイメージしにくかったり、労力のわりに報われないといったイメージがあったりと、研究医に興味があるものの、一歩踏み出せないという先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、臨床医と研究医の違いや、両者の両立について、また研究医を目指すための進路や転向についても解説していきたいと思います。
そもそも研究医と臨床医の違いとは?
医師の働き方には、大きく分けて「研究医」と「臨床医」の2種類があります。研究医と臨床医は、同じ医師とはいえその業務内容や役割は大きく異なります。こちらでは、研究医と臨床医の違いについて解説いたします。
研究医
研究医とは、主に医療に関する研究を行う医師のことを指します。まだ治療法の確立されていない病気のメカニズムを解明したり、新しい治療法や新薬の開発に携わったり、臨床試験や治験を行ったりと、研究を通して今後の医学の発展に貢献する重要な役割を担います。
研究医の活躍の場は、大学や国の研究機関、民間企業などさまざまです。研究の成果は論文にまとめ、優れた発見があれば学会や専門の学術誌で発表します。
研究医は、医学の基礎研究に従事する「基礎研究医」と、臨床に携わりながら研究も行う「臨床研究医」の2種類に分かれます。
基礎研究医の場合、患者さんを直接診療する機会はほとんどありません。
基礎研究医と臨床研究医には、ざっくりと以下のような違いがあります。
| 基礎研究医 | ・基本的に臨床は行わず研究に従事する ・医学部以外の出身者も多く医師免許は必須ではない ・主に病気の原因やメカニズムの解明、医薬品の開発など医学の根本的な部分の研究を行う ・人の細胞やマウスなどを用いた実験を行う |
| 臨床研究医 | ・自らが臨床の現場に立ちながら研究も行う ・臨床にも携わるため医師免許が必須 ・主に新しい医療技術や治療法、新薬などの実用化・標準治療化を目指す研究を行う ・患者さんを対象に治験・臨床試験などを行う |
臨床医
臨床医とは、患者さんに直接向き合って診療を行う医師のことを指します。一般的に医師というと、この臨床医のことをイメージする人が多いでしょう。
臨床医は、専門とする診療科で診察や検査・治療などを行うほか、予防対策や生活指導にも携わります。コメディカルに指示を出したり、他の医療機関や介護施設と連携を取ったりと、患者さんが適切な医療を受けられるよう臨床の現場を支える重要な役割を担います。
臨床医の活躍の場は、病院やクリニックが中心になるほか、老健などの介護施設で働く臨床医もいます。施設形態や規模によって患者層が異なり、必要なスキルなども変わりますが、臨床に携わるという点は一貫して変わりません。
勤務形態は常勤のほか、非常勤・スポットといった働き方もあります。なかには開業したり、フリーランスとして働く医師もいたりと、人によってさまざまなキャリアパスが考えられます。
研究医と臨床医は両立できる?
大学病院や大学院に勤務する医師の場合、研究・臨床の両立を求められるケースがあります。職場によっては研究と臨床の両立をサポートする体制が整えられており、両方に携わることで研究と臨床の橋渡しとなることが期待されています。
また、研究所を備えた中核病院など、大学以外でも研究に対するサポート体制が整っている職場は存在します。職場によっては、連携大学院制度などを使って学位の取得を目指すことも可能です。
研究医の魅力は?
研究医は最新の医療技術に関する知見を得たり、新薬の開発に貢献したりすることができます。患者さんに直接的に関わる部分は少ないものの、医療業界を裏から支える存在として必要不可欠です。
研究成果を通してより多くの患者さんを助けることができるという点は、研究医ならではの魅力と言えるでしょう。
自身の研究が新たな治療法や新薬の開発につながれば、これまでは治療が難しいとされていた多くの患者さんの助けとなり、医学の発展に大きく貢献することが可能です。一人ひとりの患者さんに向き合い治療の助けになれるという臨床医のやりがいとは、また違った形のやりがいを感じることができるでしょう。
研究の仕事は、これまで解明されていない課題に粘り強く向き合い、様々な角度からアプローチしていく必要があります。そのため、知的探求心が強い人や柔軟な発想ができる人、失敗を恐れずにチャレンジできる人などは、研究医に向いていると言えるでしょう。
両立は負担も大きい
研究と臨床の両立には、日常の診療を通して研究テーマにつながるアイデアが得られたり、研究の知見が臨床に応用されていることを実感できたりと、双方のつながりが感じられるといったメリットがあります。また、研究・臨床の両方に携わることによって、多様な人脈を築くことも可能です。
しかし、研究はデータ収集・仮説・実験・検証、そして論文執筆・学会発表など、やるべきことが沢山あります。臨床医として日々患者さんを診療しながら、研究医の仕事も両立することは簡単ではありません。
働き方にもよりますが、日中は通常の勤務医と同じように臨床の現場に立ち、仕事の前後や休日に研究を行わなければいけないようなケースもあり、心身に大きな負担がかかる可能性もあるでしょう。両立のためには、サポート体制の整った職場に身を置くことが大切になります。
研究医を目指すにはどうすればいい?
臨床医として働くなかで研究に興味が湧いた場合、臨床医から研究医に転向することも可能です。しかし、臨床医として経験を積んでから大学院に入り直す場合、収入や時間の折り合いをつけるのが難しく、苦労することが多いのも事実です。
そのため、臨床にも研究にも興味がある場合には、臨床研修を終えてから研究に移るのではなく、初めから臨床と研究の両立を見据えた進路を選ぶのもよいでしょう。
近年は研究医が不足しているという背景もあり、研究医を養成するための取り組みも増えています。こちらでは、近年スタートした「臨床研究コース」と「基礎研究医プログラム」について解説いたします。
臨床研究医コース
臨床研究医コースは、新専門医制度の枠組みで2021年に新設された、「臨床研究医」を養成するためのコースです。
2018年にスタートした新専門医制度は、当初は研究医を養成する仕組みが存在せず、日本の将来的な医学水準の低下が懸念されていました。そこで、臨床に携わりながら研究を行う臨床研究医の養成を目的に新設されたのがこの臨床研究医コースです。
臨床研究医コースでは、基本的な臨床スキルの習得と医学研究を並行して行うことが可能で、専門医の取得だけでなく学位の取得も目指せます。
通常の専門研修を受けた後に大学院などに進学して研究に携わる場合、一般の大学院生と同じ扱いとなり大学院からの給与は受けられませんが、臨床研究医コースでは研修期間中の医師としての身分・給与が保証されるため、研究に専念できるのが大きなメリットです。
これまでは修了要件の厳しさもあり、定員割れや応募人数の減少が続いていましたが、2024年度からは研修期間や論文執筆義務が緩和されることが決定しています。研修期間を通して研究者としての素養を身につけ、将来的に優れた研究成果を修めることが期待されています。
基礎研究医プログラム
基礎研究医プログラムは、厚生労働省が2022年より募集を開始した「基礎研究医」を養成するためのプログラムです。
日本の基礎医学分野における国際競争力は低下傾向にあり、医学部出身の基礎医学研究者の割合を高める必要性からスタートしたのがこの基礎研究医プログラムです。
基礎医学に関心を持つ研修医を対象に、臨床研修と基礎研究が両立できる環境を提供し、優れた基礎研究医を養成することを目的としています。
プログラムは基幹型臨床研修病院である大学病院に設置され、一般のマッチングに先行して別枠で募集されます。プログラムの詳細は研修先によって異なりますが、各科目での臨床研修に加えて、必ず基礎医学分野での研究期間が設けられているのが特徴です。待遇は他のコースの研修医と変わらず、研修医期間から基礎研究に携わることが可能です。
基礎医学に従事する予定であっても、臨床研修を修了することで診療を行うことが可能になり、将来的なキャリア形成の幅を広げることが可能です。また、臨床研修を通して現場のニーズを知ることが、その後の基礎研究に役立つこともあるでしょう。
研究医に転向する際のポイント
先述の通り、臨床医と研究医は業務内容や役割が大きく異なるため、働き方や待遇にも違いがあります。こちらでは、臨床医から研究医に転向する際のポイントを解説いたします。
臨床医より年収は低い傾向がある
厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、令和4年度の医学研究者(基礎研究医)の平均年収は約703万円となっています。
一方、独立行政法人 労働政策研究・研修機構「勤務医の就労実態と意識に関する調査」によると、臨床医の平均年収は1,000万円を超えるケースが多いです。
職場によっても変わりますが、研究医に転向すると臨床医時代と比べて年収が下がる可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。ただ、同時に研究医は臨床医と比べると労働時間は短くなる傾向があるため、ワーク・ライフ・バランスという面では研究医の方がバランスを取りやすいかもしれません。
研究医の職場は幅広い
大学病院・大学院・研究機関・製薬会社など、研究医にはさまざまな職場があります。職場によって研究できる内容が変わるのはもちろん、雇用形態や労働条件なども大きく異なるため、よく確認したうえで応募する必要があるでしょう。
たとえば、アカデミアと企業を比べた場合、雇用の安定性や給与水準・福利厚生などは企業の方が厚待遇となることが多いようです。一方、研究の自由度に関してはアカデミアの方が高い傾向があり、営利にとらわれず時間をかけて研究に向き合える環境があるようです。
また、企業に研究医として就職する場合、一般的に「博士号の取得」が要件となることが多いようです。
まとめ
今回は、研究医の役割や臨床医との両立、進路選択・転向などについて詳しく解説いたしました。
医師には臨床医のほか研究医として働く道もあり、同じ医師であってもその役割は大きく異なります。臨床医は医療現場を支える存在として、研究医は医療の発展を支える存在として、共に医療業界にとって必要不可欠です。
臨床医として働くなかで研究に興味が湧いた場合、大学院に入り直して研究医に転向することも可能です。また、臨床にも研究にも興味がある場合には、医学生のうちから研究を視野に入れた進路選択をするのもよいでしょう。近年は研究医不足という背景もあり、臨床と研究の両立をサポートするための取り組みも増えています。
自身が臨床と研究のどちらに向いているかは、経験してみないと分からない部分も多いでしょう。臨床医から研究医への転向、逆に研究医から臨床医への転向、そして研究も臨床も両立する働き方など、選択肢は一つではありません。様々なパターンを考えながら、納得できるキャリア形成を目指しましょう。